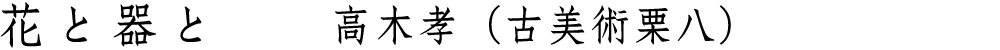
73 常滑経塚破壺

花器は平安時代の常滑広口壺で、焼成時の高温に耐えられず、ひしゃげてしまい、窯場に捨てられていたものです。大きく潰れていますが、胴は健在で、欠けや割れ継ぎ等の補修もありませんから驚きです。流れる様な自然釉まで残ります。馴染みの蒐集家から、「花器にしたい」と譲ってもらいました。屋上のプランターで育てている野花では、この壺に太刀打ちできる花はなかなか思い浮かばなかったのですが、冬を越えて残っていたアケビの蔓から芽吹きが始まりましたので、挑戦してみました。柘榴やレモンはプランターでも実をつけるので、アケビも実が成ったら愉快だろうと植えてみました。小さくてかわいい地味な花は咲くのですが、何年経っても実がつきません。ネットで調べてみると、2本のアケビを植えて受粉させる等、いろいろと手間をかけないと実はつかないことが分かりました。山道等で見かけるアケビは、自然界の様々な恵み(要素)が積み重なって、あの甘く豊かな実をつけているのですね。
「常滑経塚壺」の名は、この形の広口壺が、平安末期に埋納された、写経を納めた経筒の外容器として広く使われてきたため、そう呼ばれています。

*この連載は、高木孝さん監修、青花の会が運営する骨董通販サイト「seikanet」の関連企画です
https://store.kogei-seika.jp/

