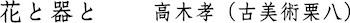
69 時代亜字形華瓶

鎌倉時代の華瓶で、姿、金味、状態、時代感ともに素晴しく、昵懇の蒐集家に無理を言って譲っていただいたものです。笹は、鎌倉谷戸の小道に群生していた中から小さな1本を根ごと引き抜き、店の裏の、五輪塔や石仏を据えてある小路に植えたものです。10センチほどの弱々しい若笹で、無事に根付いてくれるか心配していたのですが、植えてから数年で数本の笹が伸びてくれるようになりました。五輪塔の脇で、数十センチほどの高さまで細く高く伸び、わずかに小さな葉を茂らせる様子に、私は鎌倉の若武者を重ねています。笹の名は東根笹(アズマネササ)と云うようです。

小山さんのこと その4
熱心に骨董を蒐めては学ぶ小山さんのコレクションは、10年を待たずに驚異的な充実を見せるようになりました。特注された段箱の蓋を開ければ、状態の良い元興寺千体地蔵がずらりと並び、別の段箱には真綿が敷かれ、懸仏や、仏教美術の残欠、勾玉が美しく並ぶ、といった具合です。訪ねる度にこれらの段箱を見せてもらい、あれこれと語り合うのは、私にとっては勉強にもなり、何よりの楽しみでもありました。
会話がひと段落したあと、「見せようか……」と前置きして、恭しく持ち出された品に度肝を抜かれました。美しい三鈷杵文の入る瓦片、屋根に鮮やかな朱の残る鎌倉初期の泥塔。呆気にとられている私を楽しそうに眺めながら、これらが一つ二つではなく、次々とテーブルの上に置かれます。皆、京都の有名寺院から発掘された品で、市場に現れたことはなく、民間への流出も知られていません。「どうしたの」と詰問するように訊けば、「買ってきたよ」と平然としています。「どこで」と重ねて訊けば、「秘密だよ」と悪戯っぽく笑います。
骨董屋で買う以外にも、欲しい品は直接買いに行くと云うのが小山さん独自の蒐集スタンスで、そのための旅を、若い奥さんと一緒に頻繁に続けていました。仕事の合間を縫っては車でどこへでも出かけます。「言えないけど、今ちょっと狙ってるものが……」と、小山さんからは度々聞かされていました。
骨董屋の云う「うぶい品」は、味わいであったり、状態でも言いますが、小山さんの場合は言葉そのままの「うぶい品」なのです。つまり今日まで骨董屋や蒐集家の手を経ていない、人の目にさえ触れていないようなうぶい品を探し出してくるのです。旧家等を訪ねての買い出しは、それを専門とする骨董屋もあり、「うぶ出し」と呼ばれて特に驚くことではないのですが、小山さんの場合は自分好みの品(仏教美術)のみを狙っての「うぶ出し」です。それも名の知れた社寺から直接買ってくるのですから、驚かずにはいられません。
「何でそんなことができるのか」と訊ねたことがあります。「仕事がもともと営業だから……」と応えて、「こいつ(若い奥さん)が一緒だと、相手が安心するんだよ」と笑顔で付け加えました。そのとおりかも知れませんが、それ以上の「何か」がなければ、そのような場(有名な社寺)から、それなりの品を買うことなど不可能でしょう。お金に困っている相手ではありません。「あなた(小山さん)がそんなに欲しいのなら……」と、相手を納得させてしまう「何か」が小山さんには備わっていたのでしょう。
今思えば、長い付き合いの中で、私自身も小山さんの持つ、その「何か」に度々触れていたように思います。
*この連載は、高木孝さん監修、青花の会が運営する骨董通販サイト「seikanet」の関連企画です
https://store.kogei-seika.jp/

