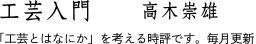


撮影|高木崇雄
3月上旬、仕事で東京に滞在していた際に、花の人・杉謙太郎さんから、急な知らせが届きました。この時期ちょうど、銀座・森岡書店にて、杉さんの花にまつわる一冊『忘草 東京』の展示会が行われていたのですが、疫病への懸念のためいったん開催を見合わせていた花会を、やはり小規模なかたちですが行います、よかったら参加ください、との誘い。〈花見にとむれつつ人の来るのみぞ あたら桜のとがにはありける〉と西行はうたったけれど、能楽『西行桜』で桜の精が西行を問い詰めたように、桜に咎はないし、ウィルスに意思などあるはずもない、咎ってどこにあるのかな、などと考えつつ、何はともあれ訪ねることにしました。かつて、店を始めたばかりの僕に、歳も変わらないし、きっと君たち二人でできることがあるよ、と言って福岡・うきは市出身の杉さんを僕に紹介してくれたのは、珈琲美美の森光さん(本連載第11回参照)です。当時すでに自身の稽古場を持ち、坂田和實さんからの信頼もあつく、福岡において ”as it is” の蔵品を展示する会が行われた際には展示を担当するなど、その才を遺憾無く発揮していた杉さんと出会い、語り合い、そして、古いものと杉さんの花を取り合わせた会を行うことで、展示や空間のあり方について多くを学びました。そののち、「時分/自分の花」を捨てるためか(と、僕は見ていました)、彼が稽古場を閉め、福岡を離れ、修行に出てからはしばらく音信が途絶え、2013年に ”as it is” で行われた花会に誘われた際も飛行機が爆弾低気圧で飛ばず。きちんと会って話ができたのはどれほどぶりでしょうか。
内田輝さんが弾くクラヴィコードが静かに響く暗がりのなかで、久しぶりに眺めた杉さんの花に対する印象は、花を問いとして提示するようになった、ということでした。以前は手の切れるような花、美しさとは何か、その答えはこれだ、とでもいうかのように美に向かってまっしぐら、という花だったのが、そうではない。本人も、奥山晴日氏による写真、内田輝さんによる音楽によって構成された書籍について曰く、この本のどこがいいのかは自分でもよくわからないし、写っている花が美しいかどうかもわからない、そもそも細部まで判別できるような写真でもなくて、写っているのは、記憶と忘却としての花なので……、とどこか決めきれないようすです。花会の最後は、桜を〈真〉とした「たてはな」でしたが、ゆとりのある〈真〉で、眺めていると花と周囲との輪郭がぼんやりと滲むような花でした。ただ、それは決して、ピントがずれている、ということではありません。オランジュリーに行って、目の前に広がる『睡蓮』をぼんやりと、包括的に眺めていると、急に奥行きが広がって風が吹く、あの感じに似ています。もちろん、杉さんが花を扱う一つ一つの動作に逡巡がある、ということでもありません。技量的な達成はもとより前提とした上での話です。
ただ、彼が「じぶんの花」から世阿弥がいうところの「却来花」、あたりまえの花をあたりまえに入れる境地に至った、いやいや、もはや名人だね、などと簡単に捉えてしまっては、どうも面白くない。そんなうまい話はないし、そこまで持ち上げてもしょうがない。なるほど、今の杉さんには「以前の負けず嫌いな精悍な面魂はどこかに影をひそめ」といった風情はありますが、「なんの表情も無い、木偶のごとく愚者のごとき容貌に変っている」(中島敦『名人伝』)ということもありません。ともあれ、どうも彼には、「名人」や「天才」といった、ことさらショウアップされた呼び名がふさわしいとも思えず、ただ、彼の花に接するものに対して、枠に嵌めてしまうことをためらわせる何かは、ある。それゆえ、彼を「花人」や「華道家」といった制度的な職名で呼んでしまうことにもまた、ためらいが残る。その印象は続く3月末、福岡・うきは市に所在する美術評論家・河北倫明の生家において行われた花会でも続きました。
*続きは以下より御購読ください(ここまでで記事全体の約半分です)
https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=335

