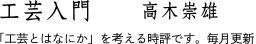


さる六月七日、ちょうど仕事で関西にいたこともあり、ほぼ二十年ぶりに「澪の会」にうかがうことができました。「澪の会」は京舞井上流・五世井上八千代による、試演会とでもいえば良いのか、祇園・新門前の自邸敷舞台にて年に数回行われる京舞と座談の会です。装束は用いず着流し、音曲は録音テープ、という素っ気なさですが、それが稽古であり、微細な移り変わりを自ら知るための定点というものでしょう。曲は地唄『八島』および長唄『白露』を八千代が、また、合間に娘の井上安寿子が上方唄『扇奴』をそれぞれ舞いました。
『八島』は能楽『八島/屋島』に則り、「今日の修羅の敵は誰そ」以下は仕舞とほぼ同一ですが、仕舞が能の一部分を切り出したものとすれば、こちらは能の後半全体を十五分程度に圧縮した体で、より緩急が高まります。また、能であれば翔(カケリ)と呼ばれる一段落は、おおむね修羅道の苦しみを表現した舞とされますが、勝修羅とも呼ばれ、祝言にも用いられる八島ゆえか、同所をしっかと拍子を踏み重ねていく、まさに地を踏みしめ鎮める反閇として舞う姿は「三番叟」の鈴之段とも通じ、見事の一言。
また、『白露』は大正八年に作曲された「新作」です。詞は露の恵み・功徳を讃えるいわば「露賛歌」であり、美文ではありますが、その美文がかえって情緒に流れやすいだろうな、と思わせる弱さがあります。能楽でいえば『胡蝶』のような軽い趣きの曲、若く華やかな女性が舞うことを想定した曲でしょうが、それを八千代はいわば『芭蕉』のように扱いました。「露という言葉が連想させるイメージ」としてのはかなさ、みずみずしさではなく、〈ただ単に、はかないものを感ずるといった、王朝的な、生活感情としての無常への詠嘆や虚無ではない。あらゆる物が、生まれ、死ぬ、咲く、散る、といった現実の世界の現象、その移り変わり〉(観世寿夫「『芭蕉』と禅竹」『心より心に伝ふる花』)という、離合集散する現象の一つ「露そのもの」として、「しほれたる風体(世阿弥)」を舞いきったのが眼目であったかと思います。
つらつらと書いてきましたが、舞台評を書きたいわけではありません。ただ思います。もっとも見ていた時期の五世八千代(当時三千子)の舞台には堅さがあり、上手ではあるが名手とは言いがたかった。けれども今あらためて見れば、堅さは別に失われたわけではなくとも芯の重さに移り、その重さは祖母、四世井上八千代(愛子)の芸とつながっている。一つ一つの型に四世の姿を覚えつつ、同時にまた、五世の芸がはっきりとある。芸とは不思議なものだ、ということです。
京舞井上流は京都五花街の一つ、祇園甲部をつかさどる流儀であり、能楽との密接な関係でも知られています。四世井上八千代の夫は観世流の能楽師である片山博通、そして当代八千代の父はその長男・片山幽雪(九世片山九郎右衛門/博太郎)。弟は十世片山九郎右衛門(清司)、夫は九世観世銕之亟(暁夫)というなかなかの濃さです。
*続きは以下より御購読ください(ここまでで記事全体の約半分です)
https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=357

