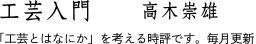


坂田和實著『ひとりよがりのものさし』より
ずいぶん以前、とある骨董商の方と話していて、「……ものの良い悪いというのはそう難しくないけど、どうしてもこういう仕事はしんがんを求められますからね……」と言われたのを「心眼」と聞き間違えたことがあります。見えないものまで見ないとならないのか、大変ね、と思ったのですが、当然その方は「真贋」の話をしていたのです。ただ、落語に「心眼」という演目があるため、また当時「見えない」ということについて考え、点字を貼ったルービックキューブを目隠しして解く、などということを試みていたため(手の感覚がかなり変わります)、つい引きずられました。落語の「心眼」は目が見えないという状況にまつわる「美しさ」を巡る人情噺で、八代目桂文楽による名演と、「盲というのは不思議なものだね、寝ているうちだけ、よーく見える」という下げが知られています。そして思うのです。ではいま、僕らは寝ているのか、覚めているのでしょうか。見えるとは何か、と。自分自身がそれを克服できているわけではないので、言いたくないというか、弱みをさらしているとしか言いようが無いのですが、自分も行っているような「ものを選ぶ」仕事における最大の弱みは、「最終的に『見える私』の優越性が残ること」ではないかと思う時があります。
たとえば、坂田さんが古いボロ雑巾に美しさを見出す、というのはわかります。たしかに美しい。ただ、だからといってそれを僕が壁に貼って飾る、というのになんとなく抵抗があるのです。もちろん、飾るのもいい。飾るという行為も暮らしなんだから、花をいけるように、雑巾も飾ればいいと思う。ただ、それがいくら美しくても、あくまで雑巾なのだから、その雑巾でもっと掃除をした方がいいんじゃないかと、ふと自省する。部屋もきれいになるし。使い終わったら洗って、その上でまた壁に貼るなりしたい。そして飾ることも出来ないくらいぼろぼろになったら、飾るよりも、燃したらいいのではないかと思ってしまう。掃除という仕事のなかで酷使された道具に偶々見いだされた美しさが、見いだされたが故に掃除から切り離されるのが、なんとなく腑に落ちない。「飾られるもの」として固着することに納得できないのです。
「工芸」を道具として考えるならば、どんな「工芸品」にもそれぞれ本来持って生まれた固有の役割があります。雑巾が工芸品かはひとまずおくとして、雑巾であれば、掃除のため、という。それが、その役割から「見える」人の目によって、切り離される。そして、切り離されて「美」としての新しい記号をまとわされることになる。つまり、雑巾が壁に貼られた瞬間に、雑巾が掃除という場に戻れなくなってしまう。そのことに不安を抱くのです。「美」が記号化されてしまい、そして、記号としてしか「見えない」人があがめてしまうことで、近代美術が陥った罠である、美の絶対優位性に「工芸がもたらす美」もまた嵌ってしまうことになりはしないか、と。
*続きは以下より御購読ください(ここまでで記事全体の約半分です)
https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=352

