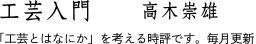


撮影|高木崇雄(全て)
先日、年若い友人Iさんから、能楽において用いられる笛・能管を預かりました。彼曰く、このごろ古い記録に銘を記された能管の行方を調べており、調査の過程で出会った能管を手に入れる機会があるんですが、一人で幾つも持っていても仕方がないですし、とはいえ、某美術館の能管のように、見世物として扱われ、乾いていく笛ほどかわいそうなものもないので、しばらくの間、使ってもらえたら、と。ありがたい申し出を受けたのがちょうど梅の季節だったということもあり、このごろは天気がいいとほぼ毎日、店の裏手、福岡城址の梅園そばのベンチに座り、かつて習った「唱歌」と呼ばれる笛の譜をさまざま紐解いては自主稽古を再開しています。稽古を1日休むと取り返すのに3日かかる、と良く言われたものでしたが、まったくその通り。再開直後は「お調べ」と呼ばれる演奏前のチューニングを一通り吹くだけで、息も絶え絶え、貧血になりそうなありさまでした。とはいえ、僕の身体は僕自身よりも遥かに覚えが良いようで、しかも長年、たくさんの人の手を経た道具は使い手を支えるのも上手。預かった笛は吹き込んだ息をしっかり引き受けて、梅園いっぱいにその音を響かせてくれます。次第に、指は唱歌の通りに自然と動くようになり、もし唱歌を忘れていた箇所があったとしても、吹いているうちに指が勝手に動いて僕に正しい譜を教えてくれるようになってきました。なんというか、僕の意思で吹いているというより、笛と僕の身体がお互いを使役して、手取り足取り吹かせてくれるようで、笛という道具、唱歌という様式化された構造≒「カタ」、そして手を抜かず稽古をつけてくれた師匠のありがたさを、今になってあらためて覚えます。
そういえば、数年前に亡くなった名手、藤田大五郎氏の用いていた笛は足利義政公より拝領したと伝わる「一文字」という銘を持つ笛で、写真などで拝見する限りでは、吹き込み口が擦れに擦れて、これ、吹けるのかな、といった様相でしたが、舞台上では人笛一体、なんの衒いも迷いも見せず、ただ静かに、強く清々しい音を響かせていたものです。素晴らしい笛は素晴らしい演者と育つ。一文字もまた、大五郎氏との舞台はさぞ楽しかったことだろうな、などと思ったりします。
それはさておき。能においてたいていの稽古は師匠の物真似からはじまるのですが、僕が笛を教わったお二方のうち、今は亡き京都の師は特に、自分に似ることを求めない人でした。稽古は基本、唱歌を口頭で歌って息遣いを確認して、あとは一通り吹く、というものですが、ある程度技術が身についてからは、息の用いようが、〈能的〉であるか否か、の指摘をするだけとなりました。いやあ、その吹きようだと、ちょっとこの能の位から外れるんですな、ではもう一度、と。指遣いなどの細かな技術について尋ねると、つつまず答えてはくれるのですが、私の工夫としてはこうしてますけどな、笛との折り合いでやってるだけですし、各々やりようもありますしな、まあ参考程度に、といった姿勢をけして崩さない。ある日、ゆっくり話をする時間があったので、その理由を伺うと、まあ、稽古はですな、私が伝えられたことを伝えるのが役目なんですが、私と同じ笛を吹かなあかん、という呪いとは違いますからな、と言われ、あ、この人、自分を表現者ではなく、媒介者として捉えてるんだな、と納得しました。そしてまた、だからこそ逆説的に、師匠の師匠が吹いていた笛の調子が、この人にのみしっかりと残り、また同時にこの人しか吹けない調子があることの理由もわかった気がしたのです。
*続きは以下より御購読ください(ここまでで記事全体の約半分です)
https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=331



