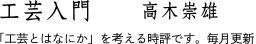


出張に出る際にはいつも、旅先での急な風邪などに備えて漢方薬を持ち歩いています。柴胡桂枝湯や葛根湯といった、ごくあたりまえの市販の漢方薬なのですが、妻の祖父が僕にのこしてくれた、大切な贈り物です。
義祖父は大阪大学薬学部を出たのち東洋医学に転じ、漢方医となったという面白い経歴の人で、幾度か僕も診てもらいました。静かな部屋で、両手で僕の両手の手首に触れ、じっと脈を診る。そして、いくつかの質問と触診ののち、体質に合うのはこの薬、風邪をひいてこういう症状だったらこれ、こういう時はあれを飲めば良い、などと幾つかのバリエーションごとに処方を出してくれました。この診断が、義祖父が亡くなった今でも変わらず役に立っているのです。なにしろ、当人が書いた本が厚生省指定の一般用漢方製剤承認基準の参考資料となっているので、ツムラやクラシエ、小太郎だろうが、市販の漢方製剤をほぼそのまま自分用に使うことができる。あいまいな物言いを嫌い、漢方薬に副作用がないなんて嘘、西洋薬が即効性で漢方薬が遅効性なんていうのも大間違い、などと通説を蹴飛ばしつつ、同時に客観的な病状の基準と治療の目標を定めることで、検証可能な〈サイエンス〉として漢方医療を位置づけることを生涯試みた姿勢のおかげかと、ただただ敬意を表するばかりです。
それにしても、義祖父が脈を診ている際の、半眼というのか、こちらのなにをどこまで見通しているのか、あるいは見ていないのかがわからない視線は、どうも忘れ得ないものです。蓮實重彦の著作『反=日本語論』の解説(ちくま文庫版)において、蓮實シャンタルは、「あるものをじっと深く見つめればそれを深さにおいて捉えることができる」〈集中的な視線〉に対する、「さまざまなものの上を揺れ動」く〈包括的な視線〉の存在について記していますが、まさに義祖父の視線は、〈包括的な視線〉、広がりと深さを同時に捉える動きだったような気がします。もちろん捉えるのは、目というよりも、手という感覚器官によるものが主ですが。
そこからさらに思い出す人が、ふたりいます。ひとりは、中学生の頃、祖母と一緒に行った鍼灸院の先生で、先生は全盲でした。暮らしている古い長屋の一室を診察室としていましたが、その部屋には、寝台の上に枕と丁寧に畳まれたタオルケット、寝台の下に脱衣籠、寝台の傍に鍼の道具と消毒器の置かれた小さな台、そしてちょっと離れた窓際に引き出しのついた小さな机と椅子があり、机上に置いてあるのは大きめのラジオと点字タイプライターだけ。治療はごく静かに、手と耳、そして鼻を使って行なわれます。鼻? と思われるかもしれませんが、伺った際に、いま、お孫さん、頬にニキビができてるでしょ、いや、においでわかるんですよ、と言われ、鍼をしてもらった(そしてすぐ治った)のです。部屋の隅で椅子に座っていただけなのに、そこまでわかるんだ、と驚かされると同時に、見えるはずないのに何でわかるんだろう、と考えた自分の鈍さを恥ずかしく思いました。見えないからより多く感じられるというよりも、見えることに頼りすぎて他の感覚を軽んじているんじゃないか、と。正しい推論ということをその時教わり、そしてまた、本人にはまったく見えず、また見られることを意識して組み立てたわけではないのに、身体の条件と仕事が一致することで出来上がる、その簡素な空間の静謐な情景にも打たれました。
もうひとりは、T.V.Raman氏です。氏はインド出身、14歳で緑内障で視力を失いつつ、インド工科大ボンベイ校からコーネル大学を卒業。以後も研究職として多くの成果をあらわし、現在はGoogleにおいてアクセシビリティ、つまり身体や経済、社会状況に関わりなく、望む情報にアクセスするための手法に関する研究を行っています。大学生の頃、ふと手に取った ”Scientific American” 誌において、Raman氏と、氏が開発した ”Emacspeak” という、音声化ソフトウェアについての紹介記事を読んで以来、ずっとその試み、そして問題意識が気になっています。
*続きは以下より御購読ください(ここまでで記事全体の約半分です)
https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=415

