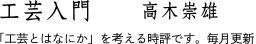


撮影|高木崇雄
以前、作り手ひとりに支払う金額を多くしたいので、あまり取引先を増やさないようにしている、という話を書きましたが、漆の仕事に関してはまだ決めきれていません。僕自身の漆器についての経験不足、そして九州という場所自体が、あまり漆の栽培に適した地質ではなかったのか、だいたいの形を焼き物でまかなうという、「椀」よりも「碗」を主に用いる土地柄ゆえかなあと思っています。お客さんもまた、漆器は毎日使うには気が引ける高級品、使ったらその都度しっかり乾かしてしまわないとすぐ傷む「ハレ」の器、という方が多く、いや、乾きすぎると逆に良くないですよ、むしろ表に出して毎日気軽に使うぐらいがちょうどいいですよ、艶が増して様子がよくなりますし、あと、漆は軽いし熱いものを入れても熱が伝わりにくいうえに、洗剤使わなくてもお湯で流せば汚れも綺麗に落ちるからかえって気軽に使えますよ、などと自分自身の体験を伝えていくことから話が始まります。ひとまずは、ひとり問屋の日野明子さんに紹介していただいて、年に一度漆の会を行い、その中からふだんの取り扱い品をひとまず決める、といった形で、今は沖縄・名護の木漆工とけしさん、岩手・八幡平市の安比塗漆器工房の仕事を常設としています。前者は夫婦二人で木地と塗りを行う暮らしぶりと人柄、そして沖縄という土地にふさわしい質感を保った仕事として、後者は、再生しつつある産地として最も可能性を感じる仕事として。
昨年11月、岩手に行き、安比塗漆器工房とその周辺を訪ねてきたのですが、九州が焼きものの国だとすれば、東北は漆の国なんだなとあらためて思いました。安比塗漆器工房自体がかつての荒沢漆器の再興を目指して作られた団体であると同時に、工房の隣には、漆に関わる技術と歴史について2年間学ぶための施設「安代漆工技術研究センター」が設けられ、漆器を作るだけではなく、漆器を作る人をも育てている。隣の二戸市にも浄法寺漆器の工房があり、さらには国産漆の大部分を産出する漆の林が管理されている。九戸郡大野には工業デザイナー・秋岡芳夫が関わった木地産地があり、さらに浄法寺は独自に木地師を育てようともしている。地元ではそんな現状を紹介する地元誌があり、配り手がいて、ブームというよりもごく普通に土地の仕事として受け入れられ、たんたんと使われている。漆に関わる一人一人が誇りを持って仕事に取り組んでいながら、一つのお椀ができたときには、いちいち個人名を取り上げて語る必要もない。語っても良いけれど、それは個人の力というよりも、ものを作る人も使う人も地域によって育てられるという、いわば「ものの生態系」の力によるもので、そのことを個々人も理解しているように見える。今、岩手で作られている漆器がすべて美しいとは言い切れない。けれどこの、岩手の漆をめぐって各々が立ち上がろうとする姿、生態系は、確かに美しい。それが産地として再生しつつある、ということです。
そこから連想するのは、調べ緒のことです。調べ緒とは、能で使われる小鼓や大鼓、太鼓の表裏の皮を締めるため用いられる麻紐ですが、小鼓の稽古をしていた頃、調べ緒を作っている方の話を聞きに行ったことがあります。その方曰く、これ、たかが縄なんだけど、この縄一つが世の中から無くなるだけで能やいろんな古典芸能の姿が変わるかもしれない、そんな気持ちで綯ってるよ、と。
*続きは以下より御購読ください(ここまでで記事全体の約半分です)
https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=381

