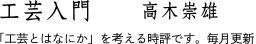
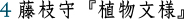

今回は〈工芸的〉な音楽として、作曲家・藤枝守の作品『植物文様』を取り上げます。
連作『植物文様』は、植物の葉の表面から得られる電位変化のデータを基に制作された音楽です。植物が生む一つ一つのデータを音符に変換し、さらに純正調やヴェルクマイスター法によるウェル・テンペラメントといった古典的音律によって試奏されるメロディ群から、心地よいと感じる主題を藤枝がひとつひとつ選びだす。そしてその旋律を束ね、反復していくなかで一つの曲ができあがる。
箏や笙、ゴシックハープやクラヴィコード、ピアノといった様々な楽器と音律によって演奏される『植物文様』は、いわゆるメシアン的な現代音楽が持つ煩さとは無縁の、心地よく、懐かしく、しかしどこか独特な和音の響きが、耳をゆっくりと、しかし確実に開いてくれるのです。
しかしまあ、その作品が心地よく、面白いのはともかくさ、音楽って〈工芸〉なの? と思われる方もいるかもしれませんので、ひとまず〈工芸〉という言葉の歴史について、かるく紐解きたいと思います。
用語としての〈工芸〉は、後晋・出帝時代に編纂された歴史書『旧唐書』(完成・奏上は945年6月)の列伝「閻立德伝」にまず登場します。
〈閻立德 雍州萬年人 隋殿內少監毗之子也 其先自馬邑徙關中 毗初以工藝知名 立德與弟立本 早傳家業 (以下略)〉
唐に仕え工部尚書から宰相となった閻立德の父・閻毗が〈工芸〉によって名を知られた旨が記されています。彼ら閻氏は陵墓の造営などで名を馳せた人々ですので、ここで用いられた〈工芸〉とは、現代における〈建築〉に含まれる造形領域すべて、といっても良いでしょう。
次いで宋代に編纂された類書『太平御覧』(977-983年頃成立)において、分類として「工芸部」の語が用いられ、以後、ものづくりの領域としての〈工芸〉の語は、近代日本において用法の変化と再定義が行われるまで、この分類にほぼ従います。なお、『太平御覧』における〈工芸〉とは、「六芸(りくげい)」、即ち「礼・楽・射・御(馭馬)・書・数」を基本とした、士大夫の備えるべき教養を指し、囲碁や絵画などもここに含まれています。
六芸といえばもちろん「道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に游ぶ」と語り、「詩に興り、礼に立ち、楽に成る」と述べた、孔子に言及せざるを得ません。なぜ孔子は「楽」を重視したか。それは、適当に楽器を鳴らすだけでは単に雑音であって、ハーモニー、和音は存在しない。音高の規則である「律」を背骨としてはじめて音楽が成立するように、社会における人もまた「礼」といった「律」があってこそ調和を得ることができる、と考えたからです。
と、いうわけで音楽もまた、工芸という領域に含んで良いのです。些か迂遠であったとはいえ。ちなみに、孔子の時代に用いられていた音律は、「三分損益法」と呼ばれる、以下のような考え方と手法によって決められました。
一本の糸を弾いて生じる音を一つの基準とすると、その糸を半分にして同じく弾くと、同じ音が、しかし高い音で鳴ることに気がつくでしょう。どれだけ半分、すなわち二分の一に短くしたところで、同じ音ですから、違う音が欲しくなる。しかも二つ弾いた際に心地よく響く和音を。ではその為にはどうするか。「二」ではなくて「三」という数字を導入し、糸の長さを当初の長さの三分の一伸ばす、あるいは三分の一縮める。つまり三分の四、あるいは三分の二の長さの糸を作り、弾いて音を得る。新たな音から先ほどの経緯を幾度か繰り返すと、一つの糸、つまり一オクターブを基準として、12の音を得ることができる。これが十二律と呼ばれる音律の基準となります。
*続きは以下より御購読ください(ここまでで記事全体の約半分です)
https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=343


