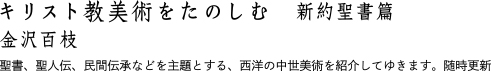
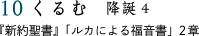

図1/「降誕」 アントウェルペン・ボルティモア四翼祭壇画の部分 1380年頃
マイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館蔵
マイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館蔵
夢に現れた天使のお告げによって、マリアの胎内にいるのは神の子と知り、安心したはずのヨセフ。しかしイエスが生まれた後も、頬杖をつき、悩んでいるようすで描かれることがあります。

図2/チロル城の祭壇画の画家「降誕」 礼拝堂祭壇画の部分 1370−72年
チロル城
なかには苦虫を噛み潰したような顔のヨセフや、チロル城の礼拝堂にある祭壇画のように[図2]、聖母子からそっぽを向いて突っ伏している姿も見かけます。民衆の間で親しまれていた宗教劇では、ヨセフは寝取られ亭主や阿呆のような役柄で登場することもあり、教会は早くも7世紀頃から、そうしたイメージを払拭しようとしていたようです。12世紀の修道士クレルヴォーのベルナルドゥスは、ヨセフがダビデ王の家系に連なることを強調し、「高貴なのは血筋ばかりでなく、その心にあり」と讃えました。

図3/マイスター・ベルトラム「降誕」 祭壇画の部分 1383年
ザンクト・ペトリ聖堂旧在 ハンブルク美術館蔵
マイスター・ベルトラムの描く祭壇画では、ヨセフが赤ちゃんイエスをマリアに手渡しています[図3]。お母さんに向かって手を伸ばすイエス。マリアさまもニコニコ。情愛に満ちた、何気ない場面に見えますが、ダビデ王の家系(救世主が生まれると預言されていた)のヨセフが、赤子をマリアに捧げているのは、旧約世界から新約世界への移行の象徴、だそうです。どうりでヨセフの顔がいかめしい。
ヨセフの地位が中世に高まるのは、ベルナルドゥスの思想を重んじた托鉢修道会(ドミニコ会とフランシスコ会)の功績です。彼らが推奨した祈禱法は、イエスの生涯を瞑想することにより信仰心を高めるというものでした。イエスの赤ちゃん人形を揺籠であやしながら祈る尼僧もいたほどです。かよわい存在としてこの世に現れた救い主。ヨセフはその守り手、養い手としての地位を得たのです。

図4/「降誕」 詩篇集挿絵 オクスフォード 1220年以前
大英図書館蔵
13世紀以降の降誕図では、マリアやイエスの世話をするヨセフが見られるようになります。図4はその最初期の例ですが、授乳中のマリアのために、ヨセフが枕の位置を整えています。

図5/ヴィシー・ブロトの画家「降誕」 祭壇画の部分 1350年
プラハ国立美術館蔵
ハンガリーで描かれた降誕図では、産婆を手伝い、産湯の準備をするヨセフ[図5]。

図6/「降誕」 アントウェルペン・ボルティモア四翼祭壇画の部分 1380年頃
マイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館蔵
ブルゴーニュ公国フィリップ豪胆公のために作られたという祭壇画です[図6]。ヨセフはマリアの傍らで靴を脱ぎ、自らの靴下でイエスの「おくるみ」を作っています。
おくるみは時代や地域によって異なり、ミイラのように(ただし顔は見える)細い麻布を巻きつけるタイプや、大きい布でくるんでから細布で固定するものなど、さまざまです。保温のためだけでなく、このようにしっかりくるんでおかないと四肢に異常をきたすと考えられてもいました。赤ちゃんの動きを制限するという、危険防止の理由もあったのでしょう。



図7/「おくるみ」いろいろ
キリストの「おくるみ」は聖遺物として崇敬を集めたようです。記録によるとパリ、ローマ、アーヘンその他、各地に(!)祀られていました。アーヘン大聖堂のおくるみは今も黄金の櫃に保管されており、7年に1度、ご開帳があるそうです。


図8/ロヒール・ファン・デル・ウェイデン「東方三博士の礼拝」 聖コルンバ三連画の部分 1455-60年頃
アルテ・ピナコテーク蔵
ヨセフが自分の靴下でおくるみを作る話がいつ頃から流布したのかはわかりませんが、14世紀前半にはすでに茶色い羊毛製として描かれるようになっています。ロヒール・ファン・デル・ウェイデンの「コルンバ三連画」のうち、「東方三博士の礼拝」場面の飼葉桶の上にあるのがそれです[図8]。
学生にこの話をしたら「お父さんの古い靴下なんてイヤ」という、つれない感想もありましたが、神の子なのに産着もなかった、キリストの慎ましさを象徴する物語なのです。

図9/コンラート・フォン・ゼスト「降誕」 祭壇画の部分 1403年
バート・ウィルドゥンゲン教区教会
そのほか降誕図のヨセフでは、マリアのためにミルク粥を作る姿も見かけます。図9は、ふうふう火を熾しながら調理中、オーツ麦の粒まで見えそう。傍らにマリアのためのボウルと木の匙も置かれていて、用意周到です。

図10/メッツのギエベールの画家「降誕」 『無畏公ジャンの時禱書』より 1410-19年
パリ国立図書館蔵
図10の降誕図では、ヨセフがお粥の椀を渡そうとしているのに、マリアも、乳母も、産湯につかるキリストも、枠の外からやってきた羊飼いのほうを見ています。

図11/「降誕図のあるP」 『典礼用楽譜』 15世紀
デュッセルドルフ大学図書館蔵
典礼で用いる楽譜の飾り文字の中にも、粥を差し出すヨセフがいます[図11]。髭もじゃ。修道女用の楽譜だったのでしょう、「P」の外で修道女ふたりが祈っています。お粥を作った鍋の傍らには猫。素朴な筆ながら、飼葉桶に寝ているはずのキリストが、ベッドでマリアと添い寝しているところなど、ほのぼのします。
中世では道化役で、聖人として扱われなかったヨセフですが、宗教改革後、とくにスペインと新大陸で聖ヨセフ熱が高まります。メキシコの守護聖人ホセもヨセフですね。

