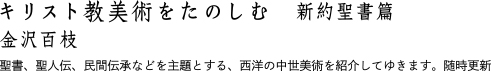
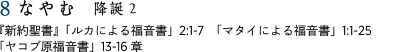
イエスの誕生について、『新約聖書』は多くを語りません。四福音書のうち言及があるのは「ルカによる福音書」と「マタイによる福音書」。どちらの記述もシンプルです。ルカは七つの節で──①ローマ皇帝が命じた人口調査のため、ひとびとは出身地に戻って登録をしなければならなかったこと ②ダビデ王の家系につらなる(とされる)マリアの夫ヨセフも、ガリラヤ地方ナザレからダビデの町ベツレヘムへ、身重のマリアを連れて赴いたこと ③旅先で月満ちて子が生まれたこと ④出産の場所がなく、赤子は飼い葉桶に寝かせられたこと──を伝えています。
歴史的にみると、この記述には矛盾があるようです。シリア州総督クィリニウスがユダヤで戸口調査を行ったのは、ユダヤがローマの属州となった紀元後6年のこと。ルカは降誕前後の事件をヘロデ大王の治世と記していますが、大王は紀元前4年に没しています。こうしたルカの「編集」は、生まれた子がダビデの家系であることを証すためにしたことのようにわたしには思われます。旧約聖書の数々の預言から、救世主はダビデの家系から生まれると考えられていたからです。
「マタイによる福音書」はさらに明確です。冒頭に「アブラハムの子ダビデの子、イエス・キリストの系図」とはあり、アブラハムからマリアの夫ヨセフに至るまでの父祖の名を列挙しているのです。ユダヤの民は父系を重んじるので、聖霊によって身籠ったマリアですが、預言の成就には、ダビデ王の子孫であるヨセフが必要だったのです。

板、テンペラ ワシントン・ナショナルギャラリー蔵
しかし、まったく身に覚えがないのに、いいなずけのお腹がしだいに大きくなってゆくのを見て、ヨセフも心中穏やかなはずがありません。中世後期に描かれた板絵に、臨月のマリアを後ろからじっと見つめるヨセフという、極めて稀な図像がありました[図1]。
ユダヤの法律では、婚約は結婚と同等の拘束力をもち、女性の姦淫は死罪に処せられました。そこでヨセフは、マリアの妊娠を公表せず、ひそかに離縁しようと決意しました。そんなときにヨセフの夢に天使が現れ、「ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである」と告げます。

大理石 ミラノ、サンタンブロージョ聖堂
ミラノのサンタンブロージョ聖堂にある現存最古の降誕図[図2]には、聖母マリアもヨセフもいません。神が人間としてこの世に現れる「受肉」の神秘を描くことを優先したためです。牛とロバがいるのは、赤ちゃんのベッドが飼い葉桶であることをわからせるため。そして動物たちが『旧約聖書』の二つの預言を体現しているから。救世主は「二匹の動物の間」に現れるという「ハバクク書」(3:2)の記述と、「牛は飼い主を知り、ロバは主人の飼い葉桶を知っている」という「イザヤ書」(1:3)の記述です。救世主となるみどり子のベッドは、飼い葉桶である必然があったのです。

ミラノ大聖堂宝物館蔵
キリスト降誕の場面にヨセフが登場するのは、わたしが知る限り5世後半以降のこと。ミラノに残る象牙彫の一部では、大工であることを示す大きな鋸を手にしたヨセフが、飼い葉桶の横に座っています[図3]。なかなかワイルドな風貌です。


フィレンツェ、ラウレンツィアーナ図書館蔵
シリアで586年に作られた『ラッブラ―福音書』の一葉には、飼い葉桶を覗き込むヨセフの姿があります[図4]。しかしこれらの表現は稀で、6世紀以降の降誕図で最も多いのは、頬杖をつくヨセフです。「頬杖をつく」しぐさについてですが、ひとつには、エヴァの創造場面のアダムと同様に、深い眠りを意味します。夢で天使のお告げを受けるヨセフですから、眠って描かれたとしても不思議ではありません。実際、がっつり眠るヨセフもよくみかけます[図5]。マリアがなにか問いかけていますが、しばらく起きそうにありません……。

オランダ王立図書館蔵

ソルソーナ司教区美術館蔵
ただし頬杖をつきながら、目を開けているヨセフも多くいます。カタルーニャ・ロマネスクの板絵[図6]でも、雲間から語りかける天使の方は見ずに、白髪でポニーテール(?)のヨセフは頬杖をついてうつむき、もの思いにふけっています。古代ギリシア以来、頬杖をつくというしぐさは「沈思」をあらわし、神々、教師、哲学者などにそうした像が残ります。

ヴァチカン図書館蔵
思案するヨセフのイメージは、「マタイによる福音書」(1:20)に起因すると思われます。新共同訳聖書では「このように考えていると」と、さらっと書かれていますが、訳によっては、「彼がこれらのことを(悶々として)思いめぐらしていると、主の御使いが夢で彼に現われて」(佐藤研訳/岩波書店)と、ヨセフが思い悩むようすをはっきりと記したものもあります。マリアの孕んでいるのは誰の子なのか。自分はそれにどう対処したらよいのか。降誕図のなかのヨセフはときにマリアに背を向け、鬱々としたようすで描かるのです。1000年頃、ビザンティン皇帝バシレイオス2世の注文により作られた写本挿絵の降誕図は、典型的なビザンティンの構図ですが、ヨセフの表情が険しい[図7]。

ノアン=ヴィック、サン・マルタン聖堂壁画
『ヤコブ原福音書』(145年頃)の記述によればヨセフは、ひとり悩むだけでなく、お腹の子が誰なのか、マリアを問いつめます。受胎告知の回でも見た通り、この外典は聖母マリアの誕生からイエスの子供時代について詳述しており、中世ではよく知られていました。ある日、帰宅してマリアの妊娠を知ったヨセフは「至聖所で暮らし、天使の手から食物を受けていたあなたなのに、どうして心を卑しめたのだ」とマリアを責めます。マリアは「激しく泣いて」身の潔白を訴えます。そんな場面を描いたのが、フランスのノアン=ヴィックにあるロマネスク壁画です[図8]。マリアさま、お気の毒に……。大勢に囲まれて責められています。

ホーホストラーテン、聖カタリナ聖堂蔵
その後、ヨセフは天使のお告げを受けて、お腹にいるのが神の子だと知り、マリアに平謝り。そんな場面を描いた稀な作例が、ロベルト・カンピン派の画家が描いた聖ヨセフ伝の一部[図9]。跪いてうやうやしくマリアの手をとり、謝罪中ですが、ものものしい大工道具が目につきます。

コンスタンティノポリス/アレクサンドリア 6世紀半ば 象牙彫 ラヴェンナ大司教区博物館蔵
『ヤコブ原福音書』には、もうひとつ愁嘆場があります。マリアの妊娠が律法学者や祭司に知られ、ヨセフとマリアは裁判所に連行されます。マリアが処女懐胎を訴えても信じてもらえず、ヨセフも婚前交渉の罪に問われました。祭司はふたりに「呪いの水」(毒)を飲ませるという神明裁判を行います。毒を飲んだふたりが死ななければ偽証ではない、ということです。ふたりは毒を飲んだ後、山に追放されるのですが、無事で、疑いは晴れます。ラヴェンナ大司教マキシミアヌスの椅子の象牙彫[図10]が表すのは、その神明裁判のようすと言われています。マリアが手にしているのが毒杯でしょうか。

ベルリン絵画館蔵
これまで見てきたヨセフの悩みは、マリアのお腹の子は誰の子か、マリアをどう処したらいいかといった人間的なことでした。しかし、聖書注釈の世界では、ヨセフが思いめぐらすのは「受肉の神秘」です。処女懐胎と受肉の最初の証人こそ、ヨセフなのです。ライン川上流域で作られた板絵では、糸を紡いでいる聖母マリアの胎内が透けて見え、金色に輝く胎児がいます[図11]。ヨセフは左のアーチから顔を突っ込んで、マリアをガン見。見る行為そのものが、ヨセフの役割なのです。

ノルウェー、ホッペルシュタ教会祭壇天蓋板絵
ノルウェーのホッペルシュタ教会にある板絵[図12]。飼い葉桶のなかにいるのはエビ天のような金髪イエス。産褥の床のマリアは、ヨセフの手にそっと触れています。こうした降誕図における愛情表現の描写は、ロマネスク以降、多様化してゆきます。

