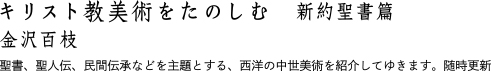
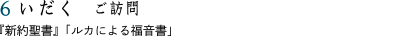

大天使ガブリエルはマリアに、彼女の従姉妹エリザベツが老齢にもかかわらず、神のちからによって懐妊し、妊娠6ヶ月であることを知らせます。そこでマリアは、ユダの山里に住む従姉妹を訪ねました(「ご訪問」と呼びます)。5世紀以降、降誕に至る物語の一部として描かれるようになりました。
エリザベツは、マリアが救世主を身籠っていると悟ります。「わたしの主のお母さまがわたしのところに来てくださるとは、どういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声をわたしが耳にしたとき、胎内の子は喜んでおどりました」(「ルカによる福音書」第1章43−44節)。マリアはこう答えました。
わたしは神をあがめ、
わたしの心は神の救いによろこびおどる。
神は卑しいはしためを顧みられ、
いつの代の人もわたしを幸せな者と呼ぶ。
神はわたしに偉大なわざを行われた。
その名は尊く、あわれみは代々、神を畏れ敬う人の上に。
これはのちに「マニフィカト Magnificat」(我が心、主を崇め)という賛歌となり、西ヨーロッパでは夕の祈りに組み込まれました。今も「マリアの歌」として親しまれています。


図1/ボッティチェルリ《マニフィカトの聖母》 1445年頃 テンペラ、板
ケンブリッジ、フィッツウィリアム美術館蔵
ケンブリッジ、フィッツウィリアム美術館蔵
「ご訪問」の場面ではありませんが、ボッティチェルリは「マニフィカト」を執筆中の聖母マリアを描いています[図1]。天の女王の冠や祈禱書、インク壺を捧げ持つ天使たち。マリアは右手に羽ペン、左手には柘榴を手にしています。柘榴は、春をもたらすギリシアの女神プロセルピナの持物で「復活」の象徴ですが、「雅歌」において処女の頬の色に喩えられたことから、聖母マリアの象徴ともなりました。懐妊中のマリアが謳った喜びの歌を、母となったマリア自身が記すというめずらしい設定ですが、聖母の涼しげな横顔の美しいこと! 幼子と聖母の指の表情も、情愛に満ちています。

図2/「受胎告知」 6世紀 ポレッチ大聖堂アプシスモザイク
「ご訪問」は御業によって身籠った二人の出会いというシンプルな場面ですが、図像はいくつかのタイプに分かれます。ビザンティン美術でよく見られるのは、エリザベツの家の外で二人が見つめ合っている場面です。クロアチアのポレッチに残る6世紀のモザイクは、やや他人行儀[図2]。

図3/ゲノエル・エルデレンの象牙彫りより「受胎告知とご訪問」 ムーズ川流域 9世紀
ブリュッセル、王立美術館蔵
ブリュッセル、王立美術館蔵
西方では、二人がぎゅっと抱き合う場面が好まれました。9世紀初めの作とされる象牙彫りでは、二人は喜びを隠せないようすで抱き合っています[図3]。この後、ロマネスク美術ではこうした抱き合うタイプが一般化しました。柱頭彫刻でも[図4]、板絵でも[図5]、壁画でも[図6]、みんな、ぎゅう。

図4/「ご訪問」 サン・ブノワ・シュル・ロワール修道院聖堂柱頭 1030年頃
フランス、サントル県
フランス、サントル県

図5/「ご訪問」 サガスの祭壇前飾り 12世紀 板絵
カタルーニャ、ソルソナ司教区美術館蔵
カタルーニャ、ソルソナ司教区美術館蔵

図6/「ご訪問」 ノアン・ヴィック、サン・マルタン聖堂壁画(部分) 12世紀
フランス、サントル県
フランス、サントル県
なかには、フランスのノアン・ヴィックにあるロマネスク壁画[図6]のように、くちびるにキスするものさえあります。抱き合うこと、くちづけすること。お互いの幸せを喜び合うさまは、正義と信仰の和合と見なされていました。


図7/ピエロ・ディ・コジモ《聖ニコラウスと聖アントニウスのいるご訪問》 1489年/1490年 油彩、板
ワシントン、ナショナル・ギャラリー蔵
ワシントン、ナショナル・ギャラリー蔵
しかし実は、「ご訪問」という主題が単独で描かれるようになったのは、1389年に神学者ボナヴェントゥーラがフランシスコ修道会の聖人暦に組み入れてからのことです。それ以後の作例であるピエロ・ディ・コジモの《ご訪問》[図7]を見ると、降誕場面は遥か遠く、図の背景左奥に小さく描かれています。


図8/「受胎告知」「マリアの旅」「ご訪問」「宿を探すマリアとヨセフ」場面 ブルゴーニュのマリアの画家『ナッサウのエンゲルベルトの時祷書』 1470年から80年頃
オックスフォード、ボードリアン図書館蔵
オックスフォード、ボードリアン図書館蔵
15世紀初め、聖母の威光を強調する構図が北方で生まれました。その流れを汲む「マリー・ド・ブルゴーニュの画家」が描いた時禱書[図8]では、マリアが受胎告知の後、エリザベツの住むユダの里へ旅をするようすと、年老いて痩せたエリザベツが少女のようなマリアに跪くようすが描かれています。ちなみに、見開きページの欄外が孔雀の羽で覆われているのは、この時禱書が、彩飾写本のパトロンとして名高いナッサウのエンゲルベルト二世のために描かれたものだからでしょう。孔雀は彼の紋章でした。

図9/ドメニコ・ギルランダイオ《ご訪問》 1491年頃 テンペラ、板
ルーヴル美術館蔵
ルーヴル美術館蔵
同様の構図は15世紀のイタリアにも伝わり、流行しました。初期ルネサンスの巨匠ギルランダイオも描いています[図9]。しかし、トリエント公会議(1545年−63年)以降、聖書に忠実でないと批判され、バロック絵画におけるエリザベツは、再び立ち上がった姿で描かれました。

図10/《ご訪問》 作者不詳 1460年頃 テンペラ、板
オーストリア、クレムスミュンスター修道院蔵
オーストリア、クレムスミュンスター修道院蔵
15世紀、オーストリア北部からドイツ南部では、特殊な図像が流行します。マリアとエリザベツのお腹の胎児が透けて見えるのです。いや、子宮が外に飛び出ていると言えばよいでしょうか。子宮内を開示するビザンティン・イコンの影響かもしれませんが、クレムスミュンスター修道院の15世紀の板絵[図10]に見られるとおり、マリアのお腹の胎児イエスはちょっとエラソーに胡座、腕組み。一方、エリザベツの胎児は跪いて祈っています。この胎児は、洗礼者ヨハネ。ヨルダン川で悔い改めを説き、キリストのために道を整える役割を果たします。
マリアの滞在期間には諸説ありますが、イタリアでは、3ヶ月間、エリザベツと共にすごし、出産を手伝ったという言い伝えが流布しています。

