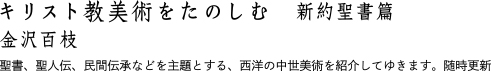
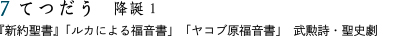

秋も深まった頃、ゼミの4年生のSさんが、困ったようすで研究室にやってきました。1枚の絵の図版[図1]を手にしています。中世の降誕図をテーマに卒業論文を書いている彼女ですが、降誕図を400枚以上も集めて分類していたら、とても変わった絵をみつけて、解釈に困っているとのこと。その写本挿絵にはイエスに祈る聖母マリアと、もうひとり、跪く若い女性が描かれているのですが、その娘には掌がないのです。そして、娘の背後に、「手」を運ぶ天使が浮かんでいました。研究室で紅茶を飲みながら、この女性はいったい誰だろうと、ふたりで首をひねりました。聖人であることを示すニンブス(光背・頭光)があるので、聖女とわかります。降誕図に登場する女性といえば、産婆のサロメが思い浮かびますが、聖母に「不敬」を働いたサロメであるはずがありません。

図1/スピッツの画家「降誕」『時禱書』 フランス 1442年頃
J. P. ゲッティ美術館蔵
J. P. ゲッティ美術館蔵
ちなみに産婆は、『新約聖書』に登場しません。産婆について言及があるのは、「ヤコブ原福音書」(2世紀)や「偽マタイ福音書」(7世紀初め)など、新約聖書の外典偽典で、現在は聖典ではありませんが、中世の頃は人気でした。前々回までの受胎告知図でも見てきたとおり、これらの文書はキリスト教美術に大きな影響を与えています。 「ヤコブ原福音書」では、出産場面を以下のように記しています。おろおろしていた夫ヨセフは産婆とゆきあい、産気づいたマリアのいる洞穴へ連れてゆきます。
そして彼らがほら穴の場所にやってくると、見よ、光り輝く雲がほら穴を覆った。そこで産婆は言った。「わたしの魂は今日偉大なものとされました。なぜならわたしの眼は不思議なことを見、救いがイスラエルに来たからです」。すると一瞬にして雲がほら穴から後退し、われわれの眼が耐えられないほどの大きな光がほら穴の中に輝いた。そしてかの光はしばらくすると後退して、赤子が現れ、その母マリアから乳房を受けた。すると産婆は声をあげて言った。「今日というこの日は、わたしにとって何という大いなる日でしょう。未だないこのような光景を見たからです。」
そして産婆がほら穴から出ると、サロメが彼女に行き会った。そこで彼女は言った。「サロメ、サロメ、あなたにお話しすべきかつてない光景があります。処女が、自然では理解出来ない子を出産したのです」。するとサロメが言った。「主なるわたしの神は生きておられます。もしわたしの指を入れて彼女の様子を調べてみないなら、処女が出産したことなど決して信じられません」。
そこで産婆ははいってきてマリアに言った。「身をととのえて下さい。あなたについて小さからぬ争いが起こったのです」。そしてサロメは彼女の中に指を入れ、叫びをあげて言った。「禍いなるかな、わたしの罪と不信仰は。わたしは生ける神を試みてしまった。ごらん、わたしの手は火で燃え落ちてしまう」。(「ヤコブ原福音書」19:2〜20:1 『聖書外典儀典第六巻 新約外典Ⅰ』 八木誠一・息吹雄訳)
サロメも産婆でした。産出産に立ち会った産婆ゼロミに比べ、立ち会わなかったサロメは聖母の処女性を疑い、産道に指を入れ処女膜を確認するという不敬に及びます。その罰として手は焼けただれるのですが、その後で御子に触れると、手は奇跡的に回復しました。
同じく外典の「偽マタイによる福音書」も同様の逸話が記されています。

図2/「降誕」 大司教マクシミアヌスの司教座装飾 6世紀
象牙彫 ラヴェンナ司教区博物館蔵
象牙彫 ラヴェンナ司教区博物館蔵
キリスト教美術ではサロメは萎えた手をもつ女として描かれます。例えばラヴェンナに残る6世紀の象牙彫。だらんと萎えた左手を訴えかけるようにマリアに差し出しています[図2]。
12世紀初め以降、俗語で書かれた武勲詩や宗教詩に、サロメでもゼロミでもない産婆が登場します。アナスタシアです。武勲詩『聖王ルイの戴冠』のなかで、ある騎士は次のように謳っています。
奇跡の都市ベツレヘムで/真の神が生まれたことはあなたを喜ばす/降誕前夜/あなたは聖アナスタシアに抱き上げられるようおはからいくださった/拝むための手もないこの女の願いを叶えてくださった
降誕に際し、聖女の手が奇跡的に回復する物語。これこそ、Sさんの絵の主題に違いありません。しかし、聖アナスタシアとは、誰なのでしょうか。同名の聖女は何人もいます。最も崇敬を集めるのは、304年12月25日にパンノニアのシルミウム(現セルビア)で殉教した聖アナスタシア。その遺体は460年にコンスタンティノポリスに運ばれ、その後1053年にバヴァリアのベネディクト会修道院に移送されると、霊験あらたかな聖遺物として多くの巡礼者を集めました。そして、ローマ貴族の娘アナスタシア。4世紀にやはりシルミウムで殉教しています。この2人は古くから混同されていたようで、6世紀の教皇グレゴリウス1世は、ローマのパラティノの丘にある聖アナスタシア(後者)に捧げられた聖堂で、12月25日の降誕の祝日にミサを行っていました。聖アナスタシア(前者)がクリスマスの日に殉教したということから、降誕にいあわせた聖女というイメージが生まれたのかもしれません。
12、13世紀に俗語で書かれた武勲詩や宗教詩で、アナスタシアはひっぱりだこです。口承で伝わっていたせいか、Anastasia, Onestasse, Honestaise、Anastace, Agnesteseなど表記はさまざま。物語にも異聞が多く、宿屋の娘、ユダヤ教祭司の娘、産婆など。しかしどの物語でもアナスタシアが手を授かる場面がクライマックスで例えば武勲詩『ラ・ヴィオレットあるいはジェラール・ド・ネヴェールの物語』では以下のよう。
あなたが生まれたとき/ひとりの貴婦人が現れた/善良な女性で/名はアナスタシア掌のかわりに切り株がついていた/主よ、彼女があなたを抱き上げたとき/あなたは彼女に手を与えてくださった/布のように白くて美しい手を
フランス語の宗教詩『聖ファヌエルの物語』では、産婆を探していたヨセフに声をかけられ、「手がない自分に何ができるかわからないけれども、ともあれ行って、できるかぎりのことはしてみましょう」と語り、出産を手伝おうとします。14世紀ドイツの宗教詩『贖罪』ではこのように。
かわいそうな娘/その名はアナスタシア/御子に仕えたかったけれど/腕がなく生まれてきた/暖かい湯を用意してあげたかったのに/御子のために/いま、みよ/アナスタシアは手と腕を授かった/何が起こったかすぐに悟った/真の神の息子が/御子が、奇跡を起こした
御子の世話をしたいけれども叶わなかったアナスタシアですが、イエスへの信仰を示すことで、「花のように美しくて白い」(『聖ファヌエルの物語』)手を授かるのです。スピッツの画家が描いたのは、まさしくこの場面でしょう[図1]。

図3/ランブール兄弟「降誕」『いとも豪華なる時禱書』 1412-16年頃
シャンティイ、コンデ美術館蔵
シャンティイ、コンデ美術館蔵
スピッツの画家の『時禱書』は、パリで制作されたものですが、ゴシックの豪華彩飾写本の代表、ランブール兄弟の『いとも豪華なる時禱書』の一葉[図3]を下敷きにしたとされます。構図も、御子の周りを天使たちが囲む表現、跪くマリアの姿勢や衣服なども似ています。スピッツの画家の写本では聖アナスタシアが加わり、ヨセフはユダヤ帽を脱いでいます。

図4/「降誕」『ホルカムの聖書』 イングランド 1350年頃
大英図書館蔵
大英図書館蔵
探してみると、降誕場面で新しい手を授かる女性の姿は他にも見つかりました。イングランドで1350年頃、ドミニコ会修道士のために作られた『ホルカムの聖書』の一葉です[図4]。ページの上段は、臨月のマリアがヨセフとともにベツレヘムの宿屋に着いた場面。宿屋の主人と娘が出迎えています。
イエスが生まれた頃のパレスチナは、ちょうど住民登録の時期でした。「全領土の住民に、登録せよとの勅令」があったのです。ヨセフも身重のマリアを連れて、ガリラヤ湖近くの小村ナザレから、はるばる出身地のベツレヘムまでやってこなければなりませんでした。しかし古都ベツレヘムの宿屋はどこも満室。『ホルカムの聖書』では、宿屋の娘アナスタシアはマリアが身重なのを見て主人に泊めてあげるように懇願しますが、断られます。善良なアナスタシアはヨセフとマリアを家畜のいるポーチへと案内します。
詞書には「すぐにアナスタシアに奇跡は起こった/彼女がイエスに触れたときに」とあります。下段の降誕場面では、生まれたばかりの御子を抱くアナスタシアが描かれているのですが、彼女の手首から、紐つきの手袋のように「古い手」がぶら下がっています。
聖アナスタシアのその後については諸説あり、娘の手が不自由でなくなったことで「これで嫁に行ける。めでたい」と父親が喜ぶパターンや、逆に彼女がキリストを信じるようになったために父親が怒り、「新しい手」を父親が切り落とそうとするパターンなど。剣を振り上げた父親の視力を天使が奪い、改心するまで光を失ったままだったとのこと。
この世の光である救世主が生まれた喜びは、中世の頃もさまざまに表されました。次回から数回にわたり、降誕図を見ていきたいと思います。

